書評:『拝啓 市長さま、こんな図書館をつくりましょう』(アントネッラ・アンニョリ)
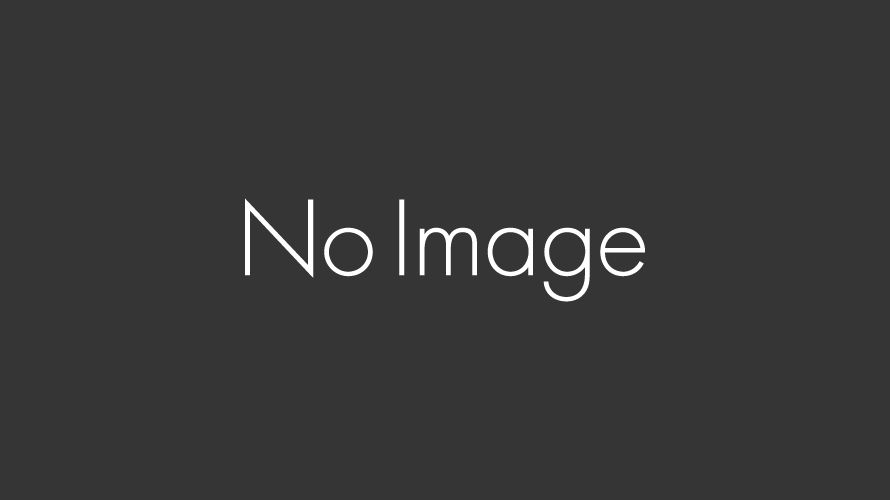
近代的な図書館づくりの思想としてスタンダードな内容だった。これから図書館を作ろうという自治体職員や首長には必読の内容といってよいだろう。
近年の各国の図書館文化や日本の大学図書館の現状に詳しい者にとっては、本書にあるもので驚くような事例はさほど多くないと思われる。日本の平均的な地方自治体の図書館しか見たことがない者には、こんな図書館がありうるのかと思われるかもしれないが、ただ、この頃のツタヤ図書館のニュースによってその数も減っただろう。
本書の主テーマは事例紹介ではなく、図書館のありかたについての思想とでもいうべきものにある。アンニョリによれば、図書館はどこまでも市民目線で、常に市民の中にあることでその価値を磨き上げていくものでなければならない。
図書館を市民にとって価値あるものとして持続させるために必要なものは何か?
それは図書館が市民のものであるという印象、確信、信念が確立され、維持されてゆくことである。設計や建築、あるいは図書館学の専門家が机上で描いただけのベストはベストたりえない。必要なのは熱意とスキルのある図書館員が新しい図書館計画の当初から持続的に計画全体に関わることであり、また市民の現在と将来の図書館ニーズを聞き出すこと、そして市民に「これは私たちの図書館である」という意識を芽生えさせるために参加の回路を開き、図書館という活動そのものに市民を巻き込んでいくことである。
「これは私たちの図書館である」と確信する人びとがいなくなったとき、図書館は死ぬ。
そもそもなぜ図書館は必要なのだろうか?
アンニョリが本書の第Ⅰ章で挙げる理由は次の通りである。
- 図書館は平等と理解、寛容を体現する施設である
- 図書館は社交の場、「知の広場」である
- インターネットは「確実さ」と「所蔵資料の安定性」を保証してくれない
- 図書館と図書館員は知的作業における手助けやガイドとなる集合的な文化環境を提供する
- 制度化された組織だけが長期的に生き延びる
- 国民の知性を涵養することなしに国の成長は望めない
- 図書館はプライバシーを侵害しない
- 社会的弱者や困窮者が生活を再建するための拠点となる
- 非デジタルネイティブな世代に対しても、インターネットの活用方法を図書館は提供することができる
図書館はいったい何の役に立つのか?
「もはやgoogle、Wikipedia、SNSといったソーシャルテクノロジーで充分ではないか?」という声に対し、図書館に比べてそれらは不確かで、個人任せで、プライバシーの懸念を常に含み、貧富の間で不平等にはたらき、そしてタコツボ的であるというのだ。
アンニョリの経歴が司書や図書館学の徒からスタートしたものではなかったことは、彼女の思想に大きく影響を与えたと考えられる。
図書館の本質は「人」と「場」にあり、「図書」はそのための装置にすぎない(主要な装置ではあるが)というのが彼女の思想の根幹にある。
この思想は概ね正しい。
日本では長らく、図書館は本を蓄積し貸し出す施設として理解されてきた。「無料貸本屋」と揶揄される所以もここにある。これは昭和38年に発刊された『中小都市における公共図書館の運営』、通称「中小レポート」による影響が大きいとされている。
公共図書館の中心を直接利用者にサービス提供する市町村の図書館であるとし、サービス維持のため高水準の資料費確保を訴えた「中小レポート」は公共図書館の普及を進めたが、一方で図書館の基本機能を「資料提供」とし、貸出冊数を公共図書館の評価指数とする風潮を招いた。
貸出冊数と来館者数のみを主要な評価指数とされたことで、日本の図書館の多くは「図書館サービスとはどのようにあるべきか」という試行錯誤を行う余地を少しずつ奪われ、本質的な機能との関係が疑わしい無意味な数値を追いかける立場に置かれることとなった。
「『刊行後半年は猛烈に回転するが以降は誰からも見向きされないベストセラー』と『5年にひとりしか借りないがそれでもその誰かのために置くべきだと思えるような専門書』のどちらを選ぶべきか?」という真摯な問いは、貸出冊数は前年比どれだけ伸びたか、という行政の掛け声の前に沈黙するしかなくなった。
少し考えればわかるはずだが、貸出冊数や来館者数はその図書館における複数の条件が影響しあった結果であり、単純に前年比増だからよい・わるいといった判断に使えるものではない。
たとえば、貸出冊数制限を倍にするだけで、貸出冊数の前年比は大きく増大するだろう。だがそれにどういった意味があるのか、数字自身はなにも語らない(実際には、一部のヘビーユーザーが新刊書を独占するようになる可能性が高い)。
また、来館するたびに特定の商業施設で値引きされるポイントがついたり、カウンターでラジオ体操のようにハンコを押してあげることにどういった意味があるだろうか。それによって来館者数が増えて、で、それは何なのか?
統計や数字が問題なのではない。それが何を意味するのか理解しないまま、数字だけがひとり歩きしている状態が問題なのだ。
私たちは図書館に何を求めているのだろうか?
アンニョリが言うような、他者と出会い市民社会を育む「知の広場」をそこに見ることはそのひとつだろう。図書館がなぜ公共施設であり、無料なのか。つきつめれば、それは自由な市民社会への意思によるのである。
また、本書ではやや軽視されているように見えるが(本書では自治体図書館に対し、蔵書数の維持にこだわらず、陳列や閲覧、または多目的に使用できるスペースを拡大することを奨励している)、著作物を蓄積することそのものが自由と自己決定を産みだし支えることは忘れてはならない。歴史上、焚書は独裁のもとで行われてきた。
図書館という限られたスペースを蔵書の保存と閲覧、またはその他の目的のために、どのように配分するかはまた、日本の場合その館のみで考えるべきでもない。
国会図書館、都道府県立図書館、市町村立図書館(中央館と地区館)、また学校図書館や大学図書館という複層的な図書館群のなかで、協力関係を結びつつ検討されるべきものだろう。
拝啓 市長さま(p7)
第Ⅰ部 拝啓 市長さま、こんな図書館を作りましょう(p11)
第一章 共有財産としての図書館(p15)
第二章 レンガ、書架、電子書籍(p59)第Ⅱ部 新しい「知の広場」(p85)
第三章 私がほしい図書館(p91)
第四章 「みんなの図書館」のつくり方(p145)第Ⅲ部 子どものための図書館(0歳から13歳)(p203)
拝啓 市長さま(p233)



