書評:『心という難問 空間・身体・意味』(野矢茂樹)
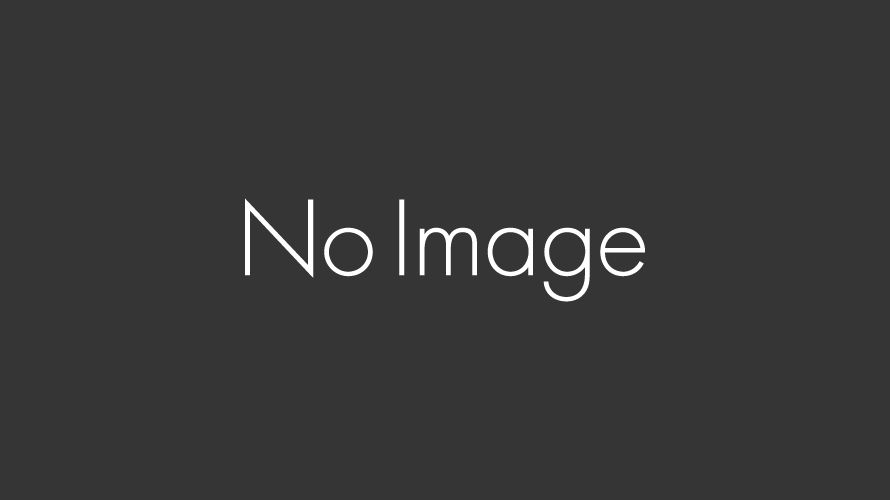
つまづき
- 私がいま経験しているものは感覚器官が得た刺激をもとに脳が作り出したもの、つまり脳内のイメージである。
- 私の経験(知覚・感覚)は私にしかわからないし、他人の経験も私には類推するしかなく、真に理解することはできない。
普段我々は、身の周りのものを素朴に「実在する」ものと思い生活しているし、他人に自分と同じように心をもった人々として接し、また彼らは自分と同じように感じ、痛みを覚えると信じて暮らしている。
だが、ふとした拍子に、ひとたびそれを哲学的に追及しはじめる。すると我々は、上記のような了解が得られるのではないか、という考えにたどり着く。
たとえば、見間違いや幻覚といった現象がある。私の普段見ているものが実在そのものであるなら、見間違いの前後で実在が変化しているのか? そんなはずはない。
生物学や脳科学の知見によれば、私たちが外界を認識するのは、視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚などを司る各種感覚器官が得た刺激が神経を通じて脳に伝わり、それらが脳で処理されることにより為される、とされている。すると、いま私たちが「現実」だと認識しているこれは、脳が作り出した知覚イメージなのではないだろうか。
なるほど、幻覚や見間違いといった現象もこの理屈で説明できる。それらは知覚イメージが誤った形に形成されてしまう現象なのだ。
見間違いや幻覚の存在から私たちの知覚のあり方をこのように推察する論じ方を錯覚論法といい、それによって導かれた、私たちの事象認識と実在とを切り分ける理論を「意識と実在の二元論」と呼ぶ。
すると、私は私の意識というスクリーンに映ったものしか見ることができない、ということか。私に見えるものは、私の感覚器を通じて得た世界の写し書きだけ。この「現実」も、そこで出会う人々とも、私がじかに接することはできない、ということになるのか?
ここに、哲学的ゾンビという哲学界の有名な直観ポンプも姿を現す。外からはまったく区別がつかないが、意識をもたない存在(=哲学的ゾンビ)を私たちは想像可能である。さて、ということなので、あなたの目の前にいる彼/彼女もまた、哲学的ゾンビでありうる。この可能性を否定しきれないことは、私たちをどこか不安にさせる。外から見て区別がつかないのであれば、問題ないのだろうか……?
また、例えば私と妻の視力や目の構造、視神経の伝達能力や、それを処理する脳の造りは異なっている。とすると、同じ絵を見ていても、彼女に見えている赤色と私が見ている赤色は、異なる色なのではないか? というより、異なるのかどうかも、どれくらい異なっているのかも、知ることが決してできないのではないか?
……ひとたびこのような哲学的考察に嵌り込むと、なにか世界の裏側が顕れたような、あるいは私たちの認識する世界がおぼろげな別の何かに感じられるような気がしてくる。
本書のテーマは、このような哲学問題の前提にある矛盾を明らかにし、経験のあり方と他者の存在をめぐる直感を見なおしてゆくことである。
そして野矢の結論を先に言ってしまおう。杞憂である。
この誤りは、「意識」という意味不明瞭な語を用いてしまったこと、あるいは、幻覚や見間違いと真正な実在との区別を説明するために、知覚イメージを想定したことから始まっている。「ゾンビ+意識=心ある人間」という足し算を成立させるような「意識」なる何ものかなどありはしないし、私たちの知覚・感覚を説明するのに知覚イメージなるものを持ち出す必要はない。
二元論の困難
私たちがなんとなく受け入れている「意識と実在の二元論」は、知覚はその原因となるものによって(たとえば実在の事物による感覚器官への刺激によって)引き起こされるという「知覚因果説」とセットになっている。つまり、私たちには直接に認識できないが刺激を引き起こす実在があり、その刺激が伝わり、統合されて、私たちの認識する「現実」=知覚イメージとなる、という筋立てだ。
いや、そのりくつはおかしい、と野矢は言う。
「私たちにいっさい認識できない実在」が、「私たちに(唯一)認識できる知覚イメージ」の原因である――どうしてそう言えるのか? 私たちにいっさい認識できない、つまりいつ・どこにあるかもわからないとある実在が、なぜ「これ」の出元であると言えるのか?
いや、と二元論者は応える。
だってそうでなければ、何が知覚イメージを形作るというのか? 知覚イメージ(あるいは意識、認知、認識世界、脳内現象……etc.)が生まれる以上、それを生む何かがあるはずだ。それが実在なのだ。
んんん?
なんだか分からないけれど、そしてそれが私たちの見ている認識する「世界」とどういう関係にあるのかも不明だけれど、実在という何らかがあり、私たちの認識する「世界」の原因となっている……?
ここで「意識と実在の二元論」と知覚因果説とによる共同戦線は行き詰まる。知覚因果説を成立させるにはそこに因果関係がなければおかしいが、二元論に立つ限りそれは永遠に見つからない。探すことすら出来ない。
この対話に臨むとき、二元論者の頭の中では、「知覚イメージは完全な実在そのものではないが、ある程度実在を反映したもの」ということが先に読み込まれてしまっている。
だが、その根拠が問われているのだ。原因=実在を私たちが直接知覚することはできない、ということがまさに二元論の中心なのだから。夢が夢であったと確証されるには、一度は夢から醒めて現実に戻らねばならない。だが二元論において、知覚イメージから醒めて実在にじかに接するといったことは起こりえない。
素朴実在論への回帰
行き詰まりのはじまりはどこにあったのだろうか?
それは、身の周りのものを素朴に「実在する」ものだと捉えることを疑い、私たちの見ているこれが知覚イメージだとしたら、と前提したことから始まっている。
ではこうしてみよう。
「私が見ているこれは、現実そのものである」。
この考え方を素朴実在論と呼ぶ。素朴実在論に立てば、私たちと世界とのつながりは整合的に保つことができる。残された問題は、
- 素朴実在論の中で幻覚・見間違いを正しく位置づけることができるか? 錯覚論法をいかに退けるか?
- 他者の痛みや、その他の感覚を理解することが私たちにはできるのか? 私が知ることのできる景色は「私がみた景色」だけではないのか?
である。
素朴実在論に立ちながら、「経験」と「他者」のすがたを掴むために野矢が彫り上げた論は2つ。眺望論と相貌論である。
眺望論
ある位置、ある視点に立ったとき現れる世界のあり方を、野矢は眺望と呼ぶ。これは"視"点というより、聴覚や触覚など五感全般に対応する概念である(視点を五感全般に一般化して「眺望点」と呼ぶ)。
重要なのは、これはその眺望点に立った主体の経験のあり方ではないということだ。ある場所からある方向を向いたとき、そこからスカイツリーが見えるということ。これは私の主観的経験ではなく、客観的な事実である。
眺望は客観的な事実であり、経験したその瞬間のみ存在するようなものではなく、私たちのうちに経験として蓄積してゆく。さまざまな視角からものを見ることで初めてその立体的なあり方を把握できるように、ある眺望点からの眺望は他の眺望点からの眺望の了解が込められてはじめて成立する。これを眺望の複眼的構造と呼ぶ。
眺望の複眼的構造はそれ自身で支えられるものではない。もう一つ必要となるのは、一人称視点的な眺望に対する、俯瞰的・見取り図的な無視点の世界了解である。私たちは現にそのような世界の見方を有している(地図や路線図、時刻表といったものはその一面である)。
無視点的に把握された世界了解に有視点的な眺望をこめた総合的な世界把握。野矢はこれを眺望地図と呼ぶ。私たちの世界認知の基底には、この眺望地図がある。眺望地図は私の知覚経験により細密化され、更新されてゆく。
知覚の理論
知覚を構成する要素として必要なものはなんだろうか。野矢はそれを対象・空間・身体・意味の4種とし、これ以外は不要であるとする。対象を知覚する際、空間・身体・意味がどのように関わってくるかによって、知覚のあり方は決定される。
空間・身体・意味のどれが主題として関わってくるかによって、野矢は知覚のあり方を三つの側面に切り分ける。上に述べた眺望論は、空間と身体を主題化したものである。特に空間を主題としたものを知覚的眺望、身体を主題化したものを感覚的眺望とする。
そして残されたもの、知覚における意味の関わり方を主題とした論が、総暴論である。
相貌論
野矢は意味的な要因によって知覚が異なる現れ方をすることを相貌と呼ぶ。
例えば同じサッカーの試合を観ていても、サッカーの戦術やこの試合がどういった位置付けの大会でのゲームなのかを知っている者と知らない者、あるいは自分の息子がその試合に出ている人と赤の他人とでは、そのみえかたが全く異なる。あるいは、そもそもサッカーというスポーツを知らず観たこともない者には、目の前の出来事がいったい何を意味しているのかさえ理解できない。
意味と物語
そして意味は、単にそれのみで存しているのではない。意味は私たちがどのような物語を生きているのかと不離の関係にある。知覚は私が生きる物語の中で意味づけられ、その意味によって相貌が現れる。
残された問題への解答
以上が野矢の眺望論と相貌論である。
眺望論と相貌論によって、残された2つの問題は次のように解決される。
素朴実在論の中で幻覚・見間違いを正しく位置づけることができるか? 錯覚論法をいかに退けるか?
例えば山道に落ちている縄を蛇と見間違えた、というとき。
素朴実在論-眺望論-相貌論に立つならば、この事例において、私は実在を直接眺望した上で、まず「蛇の相貌を持ち、かつ知覚の相貌を持つ」経験(1)をする。だがその後より正確な眺望が得られる眺望点から「縄の相貌を持ち、かつ知覚の相貌を持つ」経験(2)をすることで、先の経験が「蛇の相貌を持ち、かつ錯覚の相貌を持つ」経験(1’)へと反転するのである。
これは、経験(1)が誤った眺望だったということではない。経験(1)も世界のあり方そのものだったのだ、と野矢は言う。眺望地図は私たちの行動と認知を適切に導くためにある。だから経験(1)は眺望地図の上では経験(1’)へと更新されるが、それもまた世界のあり方そのものなのだ。
私たちは錯覚が起こりうる条件下で、正しく錯覚を経験するのである。
「他者の痛みや、その他の感覚を理解することが私たちにはできるのか」
懐疑論者が問題としているのは、私は「私の経験」しか経験しえない(私の経験するものはすべて「私の経験」である)、ゆえに、私は「他者の経験」を経験し得ない、ということであった。
なるほどこの理屈は正しい。「私の経験」はすべて「私の経験」である。だが問題はそもそも「私は他者と同じ経験を得ることができるのか」である。
眺望論と相貌論の上では、他者と同じ経験を得ることは原理的に可能だ。同じ対象を、同じ空間的関係において、同じ身体状態で知覚すればよい。同じ物語を共有していれば相貌も同じとなる。
(ここでの「同じ」に留意されたい。例えば「厳密に同じ空間的位置に立つことは不可能だ、厳密に求めてゆけば(おそらく量子レベルまで見てしまえば確実に)必ず差異が出てしまう」という反論がありうるだろう。だがその差異に、いったい何の意味があるのか?)
いや、そうではない。と懐疑論者は言う。
<誰が>経験しているかということが重要なのだ、と。
だがなぜ眺望の決定要因として<誰が>が必要になるのだろうか? 懐疑論者から納得のいく回答が得られるとは思えない。
対象・空間・身体・意味という4つの要因を共有できれば、私たちは同じ経験を得ることができるし、そこに懐疑論者が抱くような原理的不可能性はない。
以上が本書の議論の大筋である。
さらにここまでの議論の発展として、
- 他我問題(哲学的ゾンビの問題)
- 脳神話(「知覚と経験は脳が作り出したものである」)
- そして「心」とはいったい何か
について一定の解が野矢から提示される、というのが本書の内容である(それらの解についてはぜひ本書にあたっていただきたい)。
10年ほど前、『心と他者』に出会って以来、久々の野矢茂樹だった。すでに記憶もおぼろげだが、当然ながら、議論のかなりの部分がアップデートされているように感じた(プラスとクワスの説明はもはや無くてもよいということだろう)。
実のところ、ここまでまとめたがまだ十分に理解できている気がしない。特に脳神話の否定の節はいまだに腹に落とせていない。「物語を生きるのは脳ではなく人である」というテーゼは分かるのだが、しかし知覚経験の情報を統合する機能をもつのはやはり脳なのではないか? という知識が理解の邪魔をする。
「わかった」、または「野矢が間違っているのがわかった」と言えるまで、何度も噛み締めなければならないのだろう。その価値がある書である。
『心という難問』(野矢茂樹、2016年)
- 問題
- 漠然とした問題
- 素朴実在論の困難
- 二元論の困難
- 一元論の困難
- 他人の心という難問
- 理論
- 知覚の眺望構造
- 感覚の眺望構造
- 知覚的眺望と感覚的眺望
- 相貌と物語
- 解答
- 素朴実在論への還帰
- 脳神話との訣別
- 他我問題への解答
結び




