書評:『AI vs.教科書が読めない子どもたち』(新井紀子)
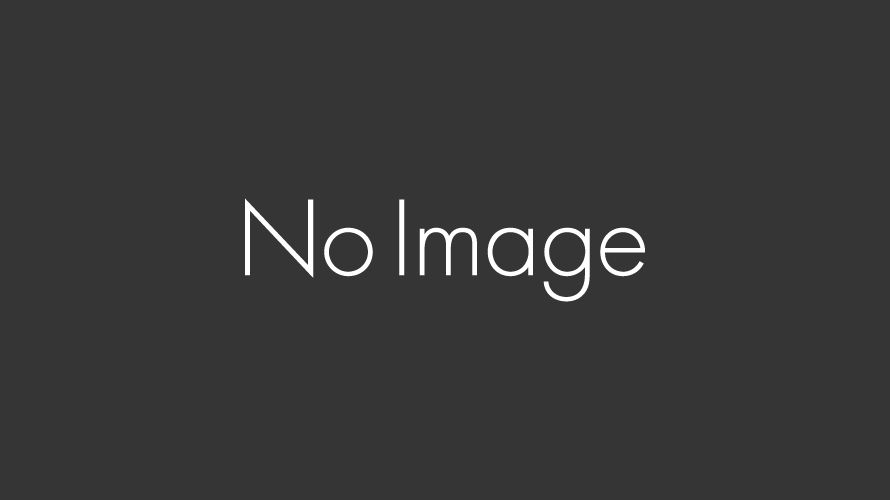
(以下、2019.12.20にBooks&Appsさんに寄稿した記事(「書籍『AI vs.教科書が読めない子どもたち』が示す、「読解力が低い人」は「認知できる世界の解像度が低い」という事実。」)の再録。未編集版のため若干文言等異なる箇所がある)
『AI vs.教科書が読めない子どもたち』を読んだ。

【2019年ビジネス書大賞 大賞】AI vs. 教科書が読めない子どもたち
本書は大きく前後半の2パートに分かれていて、
前半では、
- 巷で言われている「AI」は実際にはその実現過程で生まれた「AI技術」と呼ぶべきものであり、本来志向された意味での「人工知能」と呼ぶにははるかに足りない代物であること
- その技術の延長にシンギュラリティが訪れることも無いだろうこと
- そうであるにも関わらず、そのAI技術によって現在のホワイトカラー労働者の多くを代替しうること
- しかもそのオートメーションの波がこれまでの産業革命とは比較にならない速度で、わずか20年間に圧縮されて起こるだろう
という予測が示される。
そうであるならば、AI技術に代替されないための行動と施策を、となるのが当然の考えだ。
AI技術には実のところ3つのものしか扱うことができない。論理と統計と確率である。何故ならばAI技術とは、極論すれば数式だからだ。
AI技術は数式により構築されドライヴされる機能の集合に過ぎない。いくらGoogleの「AI」がYouTubeの無限の動画から猫画像だけを抽出してこようが、それっぽいバッハクローン曲を際限なく生成できようが、それらは計算結果でしかない。ここで意味のやりとりは発生していない。「AI」は一切意味を理解していない(と、著者は言う)。
ここから、「「AI」に奪われず残る仕事」の共通点が導かれる。著者の新井は、高度な読解力と常識、人間らしい柔軟な判断が要求される分野がそれである、とする。
しかし、その点における暗澹たる現実が本書の後半で示される。
新井が開発し実施したリーディング・スキル・テスト(RST)によれば、実に中学生の半数が、教科書を理解できるレベルの読解力さえ有していなかった。
例えば
Alexは男性にも女性にも使われる名前で、女性の名Alexandraの愛称であるが、男性の名Alexanderの愛称でもある。
問題:Alexandraの愛称は( )である。
①Alex ②Alexander ③男性 ④女性
という4択問題。
正解はもちろん①だが、正答できた中学生はわずか38%だったという。
4割近くは正答できた、ではない。4択なのでランダムに選んでも25%は当たるのだ。
興味深いのは、読解能力が低い層は、誤答の④を有意に多く選んでいた点である。
何故この間違いの選択肢を選んだのか。
「愛称」が読めなかったのではないか、と新井は推測する。読めない部分を飛ばす(このような解法は「AI」にもよく見られる)と、「Alexandraは女性である」が最も整合的な回答となる。
「愛称」の語意が分からずとも、文の構造を分析すれば上の問題を解くことはできる。
「Alexは(中略)女性の名Alexandraの●である。問題:Alexandraの●は( )である。」……この括弧にうまく嵌まるのは①しかない。
しかし、問題を解こうとした中学生のうち少なくない子らは、そうした解法にもたどり着かなかったのだった。彼らは、手持ちの認識パターンに当てはまるまでノイズをカットし、このパターンならこの選択肢だろう、という経験則=統計によって正答を「当て」ようとしていた。これでは「AI」の劣化版でしかない。
文教市場で禄を食んでいる身ながら、本書の内容は非常に衝撃的であった。我々がアクティブラーニングだのファブラボだのプログラミングだの早期英語教育だのにうつつを抜かしている間に、そんな理想とはどうにも接続されない困難な現実が、いつの間にか我々の足元で展開している。
そう言われてみれば、思い当たる節がないわけではない。
Twitterを見れば嫌になるほど目にすることになるクソリプ、もしかしてあれは、悪意や認知の歪みがあるのではなくそれ以前のレベル、つまり彼らは、そこに何が書いてあるのか純粋に読めていないのでは……?
これはちょっと怖すぎる想定である。
俺もかれこれ15年くらい、ネットでの建設的な議論や微笑ましい意見交換を楽しく眺めたり、ときにはささやかな火炎瓶を手に馳せ参じたりしてきた。火事と喧嘩は江戸の華というが、ネットではその2つをセットで気軽に味わえるので大変お得である。何よりタダなのだ。我々はインターネットを得たことでジェネリックローマ市民となる権利をも得たわけである。皇帝万歳。
江戸なんだかローマなんだかよくわからなくなったが、とにかくそんなネット空間では折に触れて話の通じない狂気じみた言説を異形の孤城のように建立する人がいて、彼らは分かりやすく話が通じないので往々にして人々の玩具にされ暗い嘲笑の贄となるのだが、その話の通じなさの核には概ね、彼らが抱く誤った固定観念や思い込み、特定の物事に関する論理の飛躍があるものだった。裏返せば、彼らは彼らなりに思想体系や意味の網目、そこから派生する理路を抱いている。ただそれが我々には共感できないものであるだけだ。
しかし翻って、上で見たような「文章が読めない人々」はそうではない。
彼らはあるレベル以上の複雑さを持つ言語世界で生きることを最初から放棄している。意味の解読にトライするコンピテンシーをあらかじめ奪われている。数え切れない大きな数が「いっぱい」としか認識できないように、複雑で抽象的な言語世界は彼らにはノイズ、あるいはせいぜい「なんだかよくわからないもの」としか認識されない。認知できる世界の解像度がそもそも異なるのである。
これって、いつからこうだったのだろうか?
この不穏な事態は近年になって起こったことなのか、それともわが国の子どもたちは昔からこうで、それが今になってようやく可視化されただけなのか?
それは本書では示されないが(何せテストを始めたのが最近なので)、気になる結果が出てきた。PISAである。
「読解力」15位に急降下、「数学」「科学」トップレベル維持…PISA : ニュース : 教育 : 教育・受験・就活 : 読売新聞オンライン
詳細は各自確認いただきたいが、前回2015年の調査と比較して、日本は「読解力」が15位(前回8位)、「数学的応用力」が6位(同5位)、「科学的応用力」は5位(同2位)と全3分野で順位を下げている。
ただし後二者は上位グループに入っていることは変わりなく、誤差範囲の順位変動なのでさほど問題ではない。注目すべきはやはり「読解力の有意な低下」(文部科学省・国立教育政策研究所)である 。
RSTとPISAで測定されている「読解力」が、厳密にはそれぞれ異なるものであることには念のため留意しておきたい。
とはいえ、メッセージを理解し、それに対して適切に応答できるかどうか、という基本線は共通していると考えてよいだろう。
俺たちはこの事態を前に何をすればいいのだろうか。
よし、私的利益の最大化だ。文盲がこんなにいるのなら、いかにもおトクな感をキャッチコピーで装いながら、実のところそうでないことが読むのに著しい苦痛を伴う長ったらしい約款にだけ書いてあるような商材を売ればいいのである。その方面に強い弁護士陣を金で揃えつつ、カスタマーサービスは精神が頑丈な体育会系をソ連方式で投入だ。もちろん約款のフォントサイズは4.5ptである。眼だ、眼を狙え。
そこまで恥知らずになることができない、我々の住むこの社会を少なくとも昨日よりほんの少し良くしたいと願う者はどうすればよいのだろう?
読解力が問題なのであれば、当然読書量を増やすべきなのではないか。やはり活字離れは本当だったのだ。
『「頭がいい」の正体は読解力』で樋口裕一氏も、「読解力が低下している原因は、考えるまでもなく読書量の減少が原因である」と書いている。その通りだ。みんなもっと本を読むべきなのだ。本と新聞を読めば読解力は高まる。こんなことは自明の真理なのである。断っておくがこの意見は俺が文教市場で収入を得ていることとはもちろん一切関係ない。俺は全くの善意から今話しているのだ。その指摘はあたらない。
さあ出版業界や新聞業界が訴えてきた活字の力を今こそ取り戻そう、読書推進運動をもう一度盛り上げよう……
が、どうもそうでもないらしい。
新井によれば、アンケートの結果、読解力と読書週間や新聞購読の有無やスマホの使用時間との間には目立つ相関が見られなかったというのだ。おかしいな、考えるまでもなく当然読書量が原因だと思ったのだが。あれれ。
もっとも、これだけ読解力が壊滅的だとアンケートの文章が理解できているのかすらも分からない。アンケートが読めてるのかどうか怪しい子たちにアンケート調査すること自体もうあんま意味ねーな、というのが新井の最終的な結論である。身も蓋も無ぇ。
じゃあどうすればよいのか?
新井によれば、読解力を養うのに有効な方法を解明した科学的研究は今のところない。
ただし、RSTで唯一分かったことがある。貧困率と読解力には強い負の相関があるということだった。
この社会から貧困を無くしていくことを除けば、処方箋はまだ分からない。
なので、我々が目指すべきところを確認しておくに留めたい。(イシューからはじめよう)

目指すべきところ? 読解力を上げることでしょ?
違う。読解力は所詮ただのスキルでしかない。
PISAを実施しているOECDは、2030 年という近い将来において子どもたちに求められるコンピテンシーを検討するとともに、それを身につけるための学びのフレームワーク(Learning Framework 2030)をまとめている。
コンピテンシーとは何か。
単純に「能力」と訳されることも多いが、スキルやアビリティといった親しみのある語彙と異なるのは、それらが単純化すれば「何ができる/できないか」に焦点を当てるのに対し、コンピテンシー概念は主体の「成果に繋がる行動特性」に焦点を当てていることである。
また成果主義とも異なり、「成果」そのものを見るのでもない。
コンピテンシーの尺度では、結果につながる行動、およびそれをもたらす心理特性、志向性が評価軸となる。
これは好奇心、創造性、集中力、オープンマインド、レジリエンス、学習に対する好姿勢、etc.といった心理特性と親和性が高い。
逆に言えば(こちらの方が分かりやすいが)、ここでは「やればできる子」は「できない子」と大差ないのである。
大事なのは「やるしできる」こと、あるいは「できるようにやっていける」ことだ。
そのような尺度の中で、OECDは具体的にどのような力を子どもたちが体得すべきとしているのか?
「世界を変革する力(Competencies to transform our society and shape our future)」である。
(いやマジで言っている)
その中で3つのコンピテンシーが「変革の力」として具体的に挙げられている。
- 新たな価値を創造する力
- 対立やジレンマを克服する力
- 責任ある行動を取る力
この3つである。
本質的なイシューは、これからの世界で求められるこうした力を身につけることだ。
読解力とはその基礎となる能力の一つなのである。
