書評:『知的トレーニングの技術〔完全独習版〕』(花村太郎)
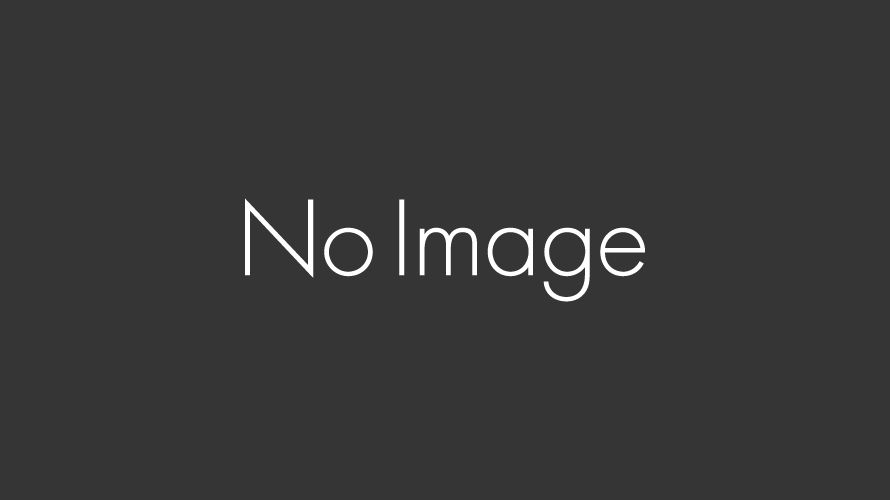
1947年生まれの著者が1980年に書いた本だと言われてやはりしっくりくる。2016年の今となっては古風と言ってよい本だし、一周回ってそれがよい(変わらぬもの、または敢えていま読むことに意味のあるもの)というところと、古くてどうにもならんというところの両面を含んだ本である。
本書の前半後半ではっきりその面が分かれていて、p260あたりがその境目だ。
そこまでは、知的な生を目指す、特に若者への素晴らしいガイド、チュートリアルの役割を見事に果たしている。
本書のタイトルにもある知的トレーニングとはなんだろうか? なぜそれが必要なのだろうか?
端的に言えば、それは自分の人生を意味づけるために必要なのである。変わり映えしない毎日の繰り返しのなかで、突然「自分はこんなことをしていていいのか、こんなことをするために生まれてきたのか」と不安が襲ってくる経験は多くのひとが共有するものだ。
花村はこれを、
知への渇望がぼくらのなかに眠っていて、それが疑問や不安や痛みのかたちであらわれているのだ(p11)
と理解する。「俺はこんなことをしていていいのか」という不安を解消するためには、「俺のすべきことはこれだ」という確信、あるいはそこまで至らずとも、「おそらくこれだ」という強い仮説をもつしかない。
そのために必須となるのは、自分を世界という横軸と時代という縦軸のなかにはっきりと位置づけることだ。「私」の生きる現代世界はいかなる時代・世界なのか? それを把握することなしに、一切と無関係な暗黒のなかで自分の生きる道を見出すことはできない。
この世界と「私」を見出す態度を花村は
世界と人生についての、自分なりの仮説と戦略を持つこと――独学・独習の覚悟(p16)
と呼ぶ。
これが本書の肝である。世界について自分で仮説を立て、それに基づき、自分で戦略を立てる。人生を全うできる(と自分が思える)かどうかはすべてここにかかっている。この原理の価値は変わることがない。
では、そのために必要なものはなんだろうか?
人生を意味あるものにするための知的トレーニングの原則として、花村は次の5つを挙げる。
- 創造が主、整理は従
- 自分一身から出発しよう、等身大の知的スタイルをつくろう
- 知の全体を獲得すること、そのために自立した知の職人をめざす
- 方法に注目する
- 情報から思想へ
この5つはゆるやかに関連している。
創造が主、整理は従
まず、インプットや方法論ではなく、アウトプットが主目的であること。ノウハウのためのノウハウに陥らないことが重要である。知的生産の方法は、答えを出す、あるいは問うための方法でなければならない。
自分一身から出発しよう、等身大の知的スタイルをつくろう
「世界について自分で仮説を立て、それに基づき、自分で戦略を立てる」。そのために必要なものはなんだろうか?
偉大な哲学思想か、網羅的百科事典的知識か、あるいは最新の宇宙物理学だろうか?
そうとは限らないと花村は言う。
必要なのは、自分の問題関心や知的サイズにぴったりあった諸道具と知的ノウハウの体系を、保持することである。(p14)
自分の現実の条件から出発して、その現実を自分の有利なほうへ変えていく戦いを通じて、自分の知的振幅は広がっていくのだ。
本書は貧乏ではあるかもしれないが貧困に陥ってはいない、ここ20年で解体されつつある「学生」という身分を主な読者層としている。花村が本書を書いた時点で、若年層がここまでの貧困状況を迎えることは想定されていなかっただろう。だがこの「現実からスタートせよ」という原理はいまも共通のものだ。世界と「私」を位置づけ、いまの「私」から始める以外に、前に進む術はない。
知の全体を獲得すること、そのために自立した知の職人をめざす
ここでいう「知の全体」とは、全知のことではない。あるジャンル、業種、領域、あるいは切り口における全体像のことである。
目の前にある簡単な事象であれ、そこにはその事象に係る全体像(俯瞰図・時系列)がある。これをつかむことができれば、その事象についてより深い理解が可能になると同時に、その事象にまつわる原理を認識できる。複雑な事象でも、構造が同じあるいは近ければその原理を応用することができる。こうして自分の知的世界が広がっていく。
方法に注目する
ある事象や問題を全体像から把握し、自ら仮説から原理へと切り開いていく独学・独習の方法は、個人の知の主体的力量を高めるトレーニングと言えるものだ。一方で道具をつくること(発明)とそれを使いこなすこと(熟練)、技術革新と熟練労働を対比し、知の分野で前者に頼ることは知的退化を招くと花村は言う。
ここから花村は古典的な知のスタイル=手仕事(ハンドクラフト)の再発見へと歩を進める。
情報から思想へ
第一の原理と似ているが、こちらはアウトプットの質を問うものだと言える。
花村曰く、
情報処理を効率よくおこなう技術というものは、ぜいたくにテマとヒマをついやして、思想をうみだすことにささげられる場合にのみ意味をもつ。(p19)
思想イズファースト。思想のないまま知的生産を効率化しても意味がないと言うのだ。
以上5つの原則を通底させながら、以降の準備編・実践編を花村は古今東西のエピソードや方法論を縦横無尽に交えながら語ってゆく。
特に、若者向けの文章であることを意識したためだが、知的生産のテクニックとしてまず「立志術」からはじめるのは新鮮に映った。
どうせやるなら本格的な仕事を、どうせなるなら一流に、というたった一回の自分の人生への大きな野心をもつこと。これが結局は、すべての原動力になる。(p44)
また立志から生まれた意欲を維持する方法として習慣化を挙げるのはセオリー通りだが、ここで例として漱石の芥川への手紙が「牛歩主義」として引用された部分は面白い。
「我々は馬になりたがるが牛になれ。世の中は根気の前に頭を下げる。うんうん死ぬほど押せ。超然として押せ」という漱石のメッセージは、なにかと効率化したがる現代の我々にますます大きな助言となっているように思える。
準備編に続く実践編でも、知的生産の方法論がわかりやすく網羅されていて読み応えがある。
ただし、p260あたりを境に雲行きがかなり怪しくなる。この時代の言論空間における「科学の限界」という観念と、その壁を超えるためにオルタナティブを目指すという思想に花村も捕らえられてしまったためだ。
現代のわれわれから結果論で言わせてもらえば、「科学の限界」など存在しなかった。というより「科学の限界」と見えていたものは、実際には当時の社会と思想の限界でしかなかった。
また、オルタナティブな思想を紹介するくだりで科学と偶然・運命、エントロピーと閉鎖系/開放系、進化論(蝶の美しい翅)、といった例から科学のゆきづまりとオルタナティブ思想の魅力を語るのだが、これらは花村の誤解や無知に基いていたり、または後の時代の科学的進歩によって次々と解答されてしまっており、一方のオルタナティブ思想のその後の沈滞と比較すると、むしろ科学の進歩的性質(それこそ牛歩主義的な)をかえって鮮やかにするという皮肉な結果になってしまっている。
ただ、それでも前半部の面白さは損なわれるものではない。
ここまで知性のある著者が、なぜ科学に対しては読み違えてしまったのだろうか?(それとも、やはり花村の読みが正しいのか?)
と考えることも、あるいはひとつのトレーニングとなるかもしれない。
目次
イントロダクション - 知的スタート術(p11)準備編 - 知的生産・知的想像に必要な基礎テクニック8章
志を立てる - 立志術(p22)
人生を設計する - 青春病克服術(p33)
ヤル気を養う - ヤル気術(p44)
愉快にやる - 気分管理術(p56)
問いかける - 発問・発想トレーニング法(p61)
自分を知る - 〔基礎知力〕測定法(p70)
友を選ぶ・師を選ぶ - 知的交流術(p85)
知的空間をもつ - 知の空間術(p97)実践編 - 読み・考え・書くための技術11章
論文を書く - 知的生産過程のモデル(p108)
あつめる - 蒐集術(p119)
さがす・しらべる - 探索術(p128)
分類する・名づける - 知的パッケージ術(p137)
分ける・関係づける - 分析術(p140)
読む - 読書術(p157)
書く - 執筆術(p200)
考える - 思考の空間術(p251)
推理する - 知的生産のための思考術(p273)
疑う - 科学批判の思考術(p298)
直感する - 思想術(p314)
さまざまな巨匠たちの思考術・思想術 - 発想法カタログ(p339)文庫版あとがき(二〇一五年 七月 著者)(p385)

