【映画感想】『ジェイソン・ボーン』に期待して裏切られたこの気持ちを一体どうしろというのか
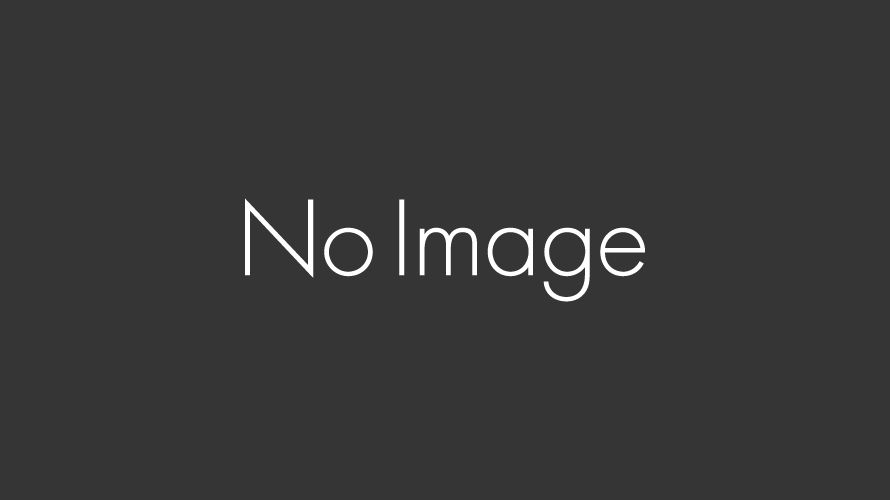
もはやスパイアクション映画の金字塔と呼んでも差し支えないボーンシリーズ3部作の待ちに待った続編ということで(ん? レガシー? なんだろう、知らないなあ聞き覚えすらない……)我々の心を焦らしてきた『ジェイソン・ボーン』がついに本日日本公開となった。
さっそく公開日初日に映画館へ雪崩れ込んだのだが、そこで俺を待っていたのはボーンシリーズっぽいが決してボーンではない何かであった……。
この気持ちをどうしてよいのかわからないので、『ジェイソン・ボーン』を観てモヤモヤした部分をここに書き記すことで少しでも心の平穏を取り戻せればと思う。
以下ネタバレあり。
前作からの時間経過がよくわからない
のっけから画面への没入を妨げたのがこれ。
今作は前作『ボーン・アルティメイタム』から何年後の話なのだろうか? それがはっきりと示されないため、せいぜい数ヶ月しか経っていないようにも、何年も経っているようにも見える。
明言がなされなくとも、画面で描かれる状況でそれが読み取れるようになっていればよいのだが、前作から引き続き登場するボーンとニッキー・パーソンズの二人はCIAから追われる身となったいわば社会の外の人間であるため、立場の変化等から時間経過を読み取りづらい。
そうなると時間の経過を示す役目を担うべきはCIAという組織や世界情勢の変化具合であるはずなのだが、前作の登場人物は上記の二人だけでCIAのメンツは丸ごと変わっている。それが時間経過を指すのか、それともCIAという組織の巨大さや人事的ドラスティックさを示したいのかが判断できない(または単にそこに意識を払われなかっただけでどちらでもないのかもしれない)。
トレーラー映像などでは「世界情勢は大きく変わった」と時代の変化が仄めかされているが、作中ではあまりそれが感じられず、相変わらずCIAが世界各地で暗闘を繰り広げていることしかわからないため、むしろ時間経過がほとんどなかったようにさえ見える。おそらく意図としては新聞をはじめとしたマスコミからIT企業やハクティビストが第一のメディアとしての座を奪ったとして時代変化を示そうとしたのだろうが、そうした舞台装置が現実世界の後追いにしかなっておらず、観客としてはどちらも同じく過去として見えてしまう。
移動と戦闘に妙味がない
ボーンシリーズの妙味が何かと問われれば、狙撃と奇襲と最新機器による追跡と撹乱が入り乱れる移動シーン、そしてその中でシームレスに移行する戦闘シーンである。
ボーンの特筆すべき能力とは権力の網をかいくぐり、物理的あるいは電子的な障壁を突破し、望むものを手に入れること、つまり探索者あるいはシーフとしてのスキルだ。
が、今作ではそのシーフスキルが発露されるシーンがほとんどない。針金だけで次々施錠されたドアを開ける後半のシーンはあるが、物理開錠はシーフの基礎スキルであって、例えば『アルティメイタム』で披露されたソーシャルハッキングじみた音声錠の解除と比べればずいぶんと見劣りしてしまう。我々観客が見たかったのは金のかかった大破壊カーチェイスではなく、新聞記者が屈んだりプリペイド携帯から電話一本かけたりするだけでCIAのエリートが慌てふためくさまである。
また、過去3作において移動シーンに緊張感をもたらしていたのは現代的権力の象徴としての監視カメラだった。しかし今作では監視カメラは移動しまくるボーンにCIAが置いていかれないようにするための舞台装置でしかなく、画面に緊張感を与える役目を果たせていない。ご都合主義すぎるかんたん監視カメラハッキングのせいでかえってその脅威のリアリティが薄れてしまったこともその一因といえる。
それから、ボーンシリーズの大きな魅力といえばブレまくる画面でのスピーディかつトリッキーな肉弾戦である。お約束による快楽など一切不要と言わんばかりに、アクション映画の文法──見栄えのする格闘術やガンアクション、決めのショットetc.──を完全無視して繰り広げられる、戦闘者たちの荒い息だけが聞こえるような生死のかかった生々しい戦闘に手に汗握り、そのへんの日用品を活用して武器を帯びた相手を制して喝采をあげるという、リアリティとショーイズムが互いに強く引き合うことで成り立っていた奇跡的なバランスがそこにあった。
『ジェイソン・ボーン』には残念ながらあまりそれが見られなかった。
マシーン=エージェントと人間=ボーンという対比がなくなった
主人公ジェイソン・ボーンの目的は一作目から変わらず自身のアイデンティティーである。記憶を失った彼は、自分はいったいどんな人間なのか、それ示してくれる情報を追う。アイデンティティーを求めるようになったことが彼と他のエージェント(要員)たちとの違いであり、人間性=アイデンティティーを捨て去って得た超人的能力が、アクシデントによって人間性の再帰へと逆行しはじめたこと──これが殺人機械じみたエージェントたちの中でボーンを際立たせるポイントであり、シリーズのテーマをドライブする原動力でもある。
ボーンシリーズのテーマを極めて雑に言い切ってしまうと「自分の安全保障のために人間性を捨てた結果がコレだよ! よい子は真似するなよ!」なので、敵役は情を浮かべることすらなく淡々と仕事をこなすエージェントであってこそ映えるのだが、今作の敵役はボーンへの復讐という情念を仕事に乗せまくることで普通に人間をやってしまっていて対比になっていない。
さすがにそれは初期三部作でさんざんやってるからというのもわからんではないが、であればエージェントを敵役に据えること自体を再考すべきだったと思う。
その新しい敵役(として巻き込まれかかる)候補として一応現れるのは作中世界での巨大IT企業ディープドリーム(どうみてもgoogle)だが、今作では単に巻き込まれるだけでガジェットとして活用されるわけではない。この辺は次作で動き出す要素として置かれているのかもしれないが、今作『ジェイソン・ボーン』では単に新しい監視システムを担う役として担ぎ出されるだけであるため、物語に馴染めていないようにみえてしまう。
今作のストーリーラインがいまいちフワフワしていたのはこの配役の散らかり具合も原因の一つだったように感じた。
CIAの人間に魅力がない
ニッキー・パーソンズ、コンクリン、アボット、パメラ・ランディ、ノア・ヴォーゼンといった過去作のCIAの人間たちは、主人公の敵役でありながらもそれぞれ立場が異なり、後にボーン側についたり、敵ではあるが職務をまっとうしようとした結果そうなっただけだったり、あるいは自身と組織の狂気に気付きながら「国家のために」とそれを良しとしてきた者だったり、それぞれに紋切り型でない魅力があった。
今作のデューイ(トミー・リー・ジョーンズ)とヘザー・リー(あんまよく知らないが美人)はノア・ヴォーゼンとパメラ・ランディの劣化コピーという感じで、ヘザー・リーが最後にひと捻りあるものの、両者とも人物造形に深みがなく、中盤以降その程度でボーンに勝てるわけないじゃん感が脳裏に漂ってしまって画面にのめり込みにくくなっていた。
CIA以外でも、ピチャイ@google感あふれるアーロン・カルーアもヘザー・リーとスタンフォード大の同期なんだよとシリコンバレー感満載の人間関係をチラ見せしたりするものの、そこ止まりであまり掘り下げもない。
ボーンの動機が弱い
ボーンシリーズ再起動にあたって必須となるのは新たな謎であり、これまでのスタイルを踏襲するため、「初期三部作で明かされた真実にはまだ裏があった」ということになった。それ自体は悪くないが、結局明かされるのはトレッドストーン作戦の責任者はボーン=デイビッド・ウェブの親父であり、しかも息子を殺人マシーンにさせないためだった(でもCIAの他派閥に偽装テロされて死んだ)、という事実であった。
トレッドストーン作戦の発案者が父だった、というネタが、ボーンを再度CIA相手に大立ち回りさせるほど引力の強い謎だったかと言われると、弱かったのではないだろうか。そのため、何のためにボーンが戦っているのかという主題自体が鑑賞者側の腹に落ちないまま話だけが進んでしまったように思う。
また、最後の敵エージェントを追うシーンだが、マリーを殺したエージェントのときと違い、実父がぽっと出のキャラなので逃げるエージェントをボーンが復讐のために追うことにも共感しきれず、逃げるならいつもどおりほっとけばいいじゃんと思ってしまった。
人間対殺人機械という対比にも徹しきれず、かといって互いを復讐相手としたドラマも掘り下げきれず、中途半端になってしまった感がある。
とりあえずここまで書いて少し落ち着いたので筆を置くことにする。
次回作には期待したい。

